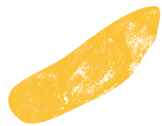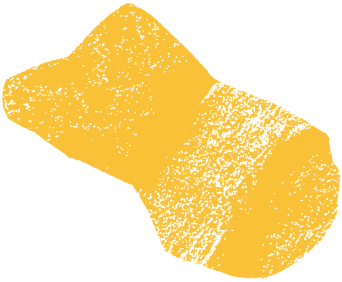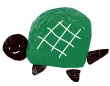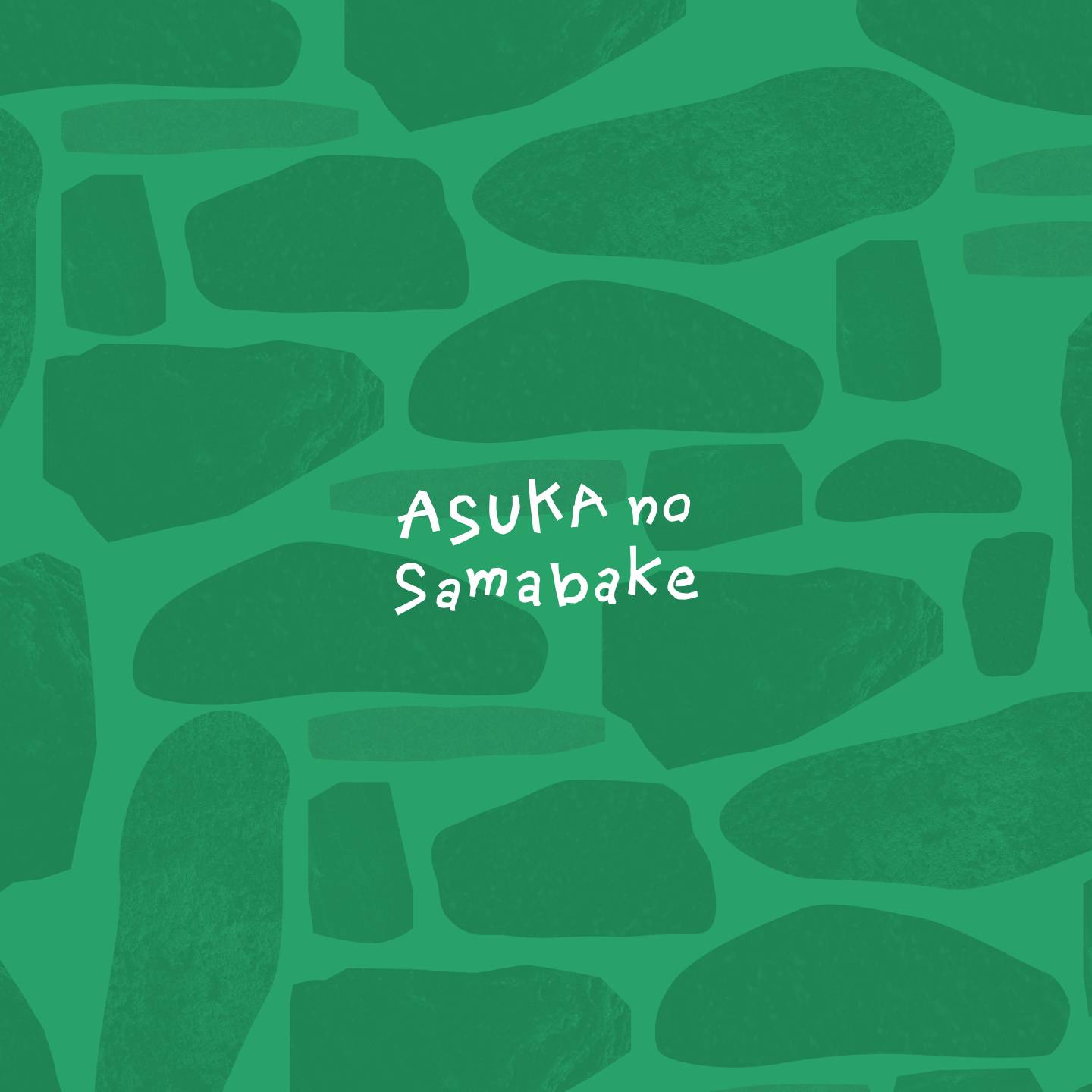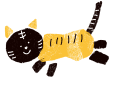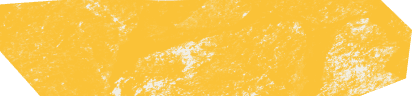サマバケ通信
samabake journal
明日香の自然がいっぱい! 草木染め&蓮の田んぼ体験!【体験レポート Vol.1】
- 文
- 坂東愛
- 写真
- 都甲ユウタ

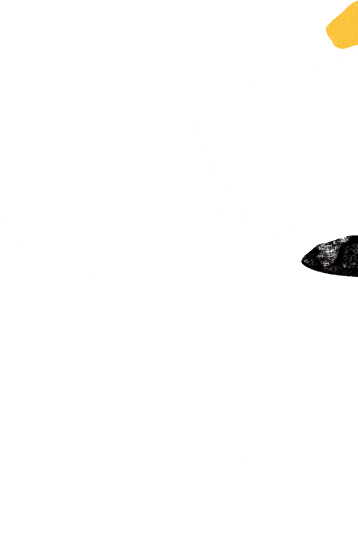



1組目のご家族は、竹田さんファミリーです。

「こんにちは!」と元気に挨拶してくれたのは、3人兄妹の悠真(ゆうま)くん・明日香ちゃん・柚香(ゆずか)ちゃんです。7歳の明日香ちゃんは、最近名前を漢字で書けるようになったことで、明日香村のことも知り、行きたいと思っていたところだったとか。ちなみに、“明日香”というお名前は、昔からあり、和歌でも使われ、響きがきれいであることなどから名付けられたそうです。
和歌といえば、現存する日本最古の歌集『万葉集』には、すでに“明日香”という言葉が地名として登場します。遡ること約1400年、飛鳥~奈良時代の歌が収められている『万葉集』が編纂され、いくつもの歌が詠まれていた飛鳥時代、ここ明日香は日本の政治・文化の中心地でした。その足跡が未だ多く残るこの地で、どんなワクワクが待っているんでしょうか。さあ、最初の体験に出発です。
明日香の植物で草木染め体験

とにかく猛暑日が続いた今年の夏。この日もあいかわらずの暑さでしたが、お住まいのエリアよりは涼しいと、竹田ママが驚いていました。と、不意に道を引き返して駆け出す悠真くん。

お目当てはどうやらトンボのようです。豊かな自然や田園風景が残る明日香には、数多くの生きものも生息しています。虫が大好きだという悠真くんにはぴったりの遊び場かもしれません。
さて、最初の体験場所である古民家に足を踏み入れると、目に飛び込んできたのは、さまざまな模様があしらわれた色鮮やかな布。すべて植物で染色されています。そう、これから体験してもらうのは、植物だけを使って染める「草木染め」です。

インストラクターは明日香で約40年、草木染めをされてきた水谷道子さん。昔ながらの手法で、竹田ファミリーはトートバッグの染色に挑戦します。


草木染めや模様の説明、植物についてのお話などを聞いた後、まずは、自分がつくりたい模様を決めていきます。

女性陣が選んだのは、子どもから大人まで幅広く人気の花柄。男性陣は、「ミツウロコ」という三角形柄に決まりました。
水谷さんによれば、壁掛けの布に配された模様は、すべて1350年ほど前からあるのだそうです。そして必要な道具は、手・板切れ・棒の3つだけ。板切れで布をはさんだ部分は着色しないことを利用し、板の置き方・布の折り方を工夫することで、多様な模様を編み出していくのです。
使う素材こそシンプルですが、図形の展開図のように、完成図を想像しながら折り方や板の置き方を決める……考えるだけで頭の中が混乱してきそうですが、兄妹は水谷さんの力も借りながら、一生懸命に布を折っていきます。


最後は板切れが動かないよう、輪ゴムでしっかり固定。これで染色の準備は完了です。
飛鳥時代にはすでに始まっていた染色。薬品などは使わず、植物の茎や根・実を刻んで煮立てた染液だけで染めていきます。「新鮮な野菜が一番おいしいように、生きているときが一番きれいな色が出る」と水谷さん。生きた染料ともいえる植物を、体験時間に合わせ、8種類準備してくれていました。

建物奥の扉を開けて外に出ると、植物が入った鍋がズラリ。コンロの火をつけ、熱中症とやけどに注意して、いざ染色スタートです。


お姉ちゃんとお揃いの色にした柚香ちゃんは、時折抱っこしてもらいながら鍋の中を覗き、様子を見守ります。


時間にして20分ほどでしょうか、染色の行程が終わりました。最後に水でゆすいで、布を広げてみると……




おお~!ちゃんと模様ついてる!


真剣な面持ちだった子どもたちが、一気に笑顔になりました。同じ赤と花柄でも、姉妹それぞれ仕上がりは違います。どれひとつとして同じには染まらないのも、草木染の魅力のひとつです。

ちなみに、お父さんと悠真君は「玉ねぎ」の皮、お母さんは「セイタカアワダチソウ」の葉・茎などを使用。田舎であれば、どれも暮らしの身近にある植物です。

実は、森林インストラクターでもある水谷さんは、森や自然を保護する活動もされています。40年前、森で間伐を行っていた際、そのたびに服に色がつくことに気づきました。しかも、洗っても落ちない。そこから、植物の色に興味を持つようになったそうです。


「色を通じて、もっと森に興味を持ってもらえるのでは」という思いから、試行錯誤を経てたどり着いたのが、ラインナップである8色。実際に煮出したとき、「こんな色になるのか!」 と実感しやすいよう、見聞きしたことのある、イメージしやすい植物が揃っています。竹田さんファミリーの作品を見ても、植物だけとは思えないような鮮やかな色味に仕上がりました。「学校に持って行く!」と、ご満悦な様子の兄妹に、こちらも嬉しくなります。

「子どもも初めての体験で、嬉しかったと思います」と話すのは竹田パパ。現代では、草木染されたものを目にする機会自体、そう多くはないかもしれません。色落ちのしにくさから普及した化学染料に対し、色褪せしやすい草木染。昔は布もとても貴重だったので、繰り返し染めることで、大事な布を使い続けました。実際、古代からある模様は、重ね染めを想定し、何回でもつけられるようなものばかりなのだそうです。

それでも、今も古臭く感じることのない模様からは、限られた状況を発想力でもって乗り越え、新たな模様を生み出していった人々の努力や熱意のようなものを感じられるような気がします。「昔の人はああいうことを普通にやってて、すごいと思った!」という悠真君の感想にも納得です。水谷さんの森への愛情と、先人たちの工夫があってこその体験ともいえるかもしれません。

最初は少し緊張気味な様子だった兄妹ですが、体験場所をあとにする頃には、「めっちゃ楽しかった!」と元気いっぱい!緊張もバッチリほぐれたようです。そして、今日の体験はここで終了。民宿脇本に少し早めに入ってゆっくり休み、明朝の体験に備えます。

大きな蓮の田んぼ体験
そして、翌日。この日は雲ひとつない快晴です。


朝7時にしてすでに汗ばむ暑さですが、風もあり、清々しさを感じます。

駐車場から少し歩いて体験場所に向かう間、竹田ファミリーの子どもたちは、昨夜はぐっすり眠れたことやごはんがおいしかったこと、宿の近くで虫を捕まえたことを教えてくれました。

しばらくすると、「大きい!」と声を上げる明日香ちゃんの目線の先に、一面に広がる田んぼが見えてきました。その中に、ひときわ大きな葉っぱが見える一角があります。ここが目的地の蓮畑です。

今日のインストラクターは、明日香村在住の迫田晃亘(さこだあきのぶ)さん。約10年前に移住され、「ココロネFARM」として自然栽培米や蓮根を育てる農業のほか、山仕事やツアーガイドなど、幅広い分野で活動されています。今日は竹田さんファミリー以外にも、2組の親子も参加し、一緒に蓮畑での楽しみ方を教えてもらいます。

蓮の近くまで行くと、空に向かってぐんと伸びる茎と葉っぱの大きさがさらに際立ちます。背丈は柚香ちゃんよりもずいぶん高く、葉っぱも大人の頭がすっぽり覆えるほどの大きさ。子どもたちが頭にかぶってみると、「涼しい~!」。天然の日よけになりました。

自分で好きな蓮の葉を手に入れるべく、これから畑に入っていきます。
今がちょうど開花ピークの蓮の花。早朝に咲き、昼には花が閉じてしまうので、この時期の朝にしかできない体験です。お米のように水を張って育てる蓮畑は、中に入ると、大人の膝くらいまでの深さになるところも。


パパと悠真君は、蓮の間をかき分けながらぐんぐん奥へと進んでいきます。ところが、姉妹は数歩ったところでストップしてしまいました。初めての泥の感触が、2人には少し冒険すぎみたいです。

心なしかしょんぼり気味の姉妹でしたが、すぐにそばを通る水路で遊び始めました。水の流れは思いの外早く、葉っぱを流せば、するすると進んでいきます。



え、すごい!


ふいに、明日香ちゃんの声が上がりました。水に流した葉っぱが濡れていないことに気づいたのです。

何度上から水をかけても濡れない葉っぱに、「なんで、なんで!」と、にわかにテンションがアップし始めた明日香ちゃん。実は葉の表面の特性により、水は水滴となって転がり続けるため、蓮の葉は決して濡れることはありません。「ロータス効果」と呼ばれるこの現象、明日香ちゃん、図らずも大発見です!
続いて、休憩を交えながら、蓮の葉を使ったお茶づくりにチャレンジ。自分で取った葉っぱを細かくちぎり、袋に入れていきます。

あとはひたすら揉みこむだけ。1日天日干ししたら完成です。美容茶ともいわれる蓮の葉茶は、クセも少なく、すっきりとした味わい。しかも、迫田さんいわく、「テキトーに作ってもイケる」ほど簡単に作れるのだそう。

もうひとつ、この時期だけの贅沢な楽しみがありました。「蓮の実」です。

お菓子や料理・薬用としても重宝される蓮の実は、口にすると、とうもろこしのような甘みがあります。ただ、どちらも少し大人の味だったのか、甘い炭酸ドリンクには勝てず……子どもたちからは「炭酸!炭酸!」と炭酸コールが始まりました。こうして気兼ねなくやりとりできるのも、迫田さんの気さくで親しみやすい人柄ゆえでしょうか。

さらに、迫田さんは蓮の茎がストローにもなることも教えてくれました。

さっそく、悠真君が挑戦……。



飲める!


勢いよくいった悠真君に対し、ゆっくり飲んだあすかちゃんは少し顔をしかめながら一言。



草の味がする(苦笑)。


どうやら、ごくごく飲むのがおいしく飲めるコツのようです。とはいえ、実際に体験してみなければ味もわからないわけで、またひとつ発見になりました。
最後に、再び畑へ。最初は泥に抵抗があった明日香ちゃんですが、蓮の葉カットに挑戦したいと、自らハサミを手に! 手前に生える蓮の葉をチョキン、見事カットできました。

そして、その葉っぱをまた水路に流します。明日香ちゃん、すっかりこの遊びが気に入ったようです。
さっきよりも遠くから流してみると、小さいカエルたちが次々と葉っぱの上に集まってきます。実は、悠真くんと違い、虫やカエルが苦手な明日香ちゃん。畑に到着早々、水路にいるカエルに怯えていた姿はどこへやら、「カエル乗れー!」と今日一番のテンションで大はしゃぎでした。


前半は家族単位で遊んでいた子どもたちも、気づけば一緒に葉っぱ流しとカエル獲りに夢中。迫田さんも思わず、「こんな遊び方もあるんだなあ」とつぶやいていましたが、子どもたちにかかれば、なんでも遊びになるようです。明日香の当たり前にある自然や畑は、今の子どたちにとっては、贅沢な遊び場なのかもしれません。

テンション最高潮の中、名残惜しくも終了の時間に。すっかり仲良くなった迫田さんと子どもたちは、楽しく話しながら帰路につきます。さわさわと風にそよぐ稲穂に、聞こえてくるのはセミや子どもたちの声だけ。静かで穏やかな時間が流れています。

そうこうする間に、お別れの時間がきてしまいました。「また会えたらいいね。」と言ってくれた明日香ちゃんと、ここで待ってるねと約束。「絶対また来る!」と笑顔でお別れとなりました。成長した3人にまた会える日が楽しみです。