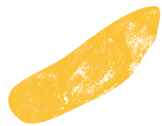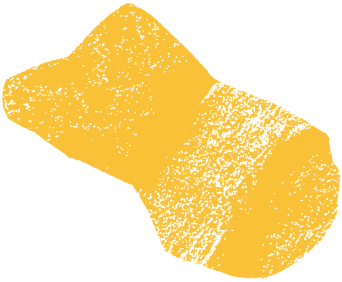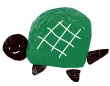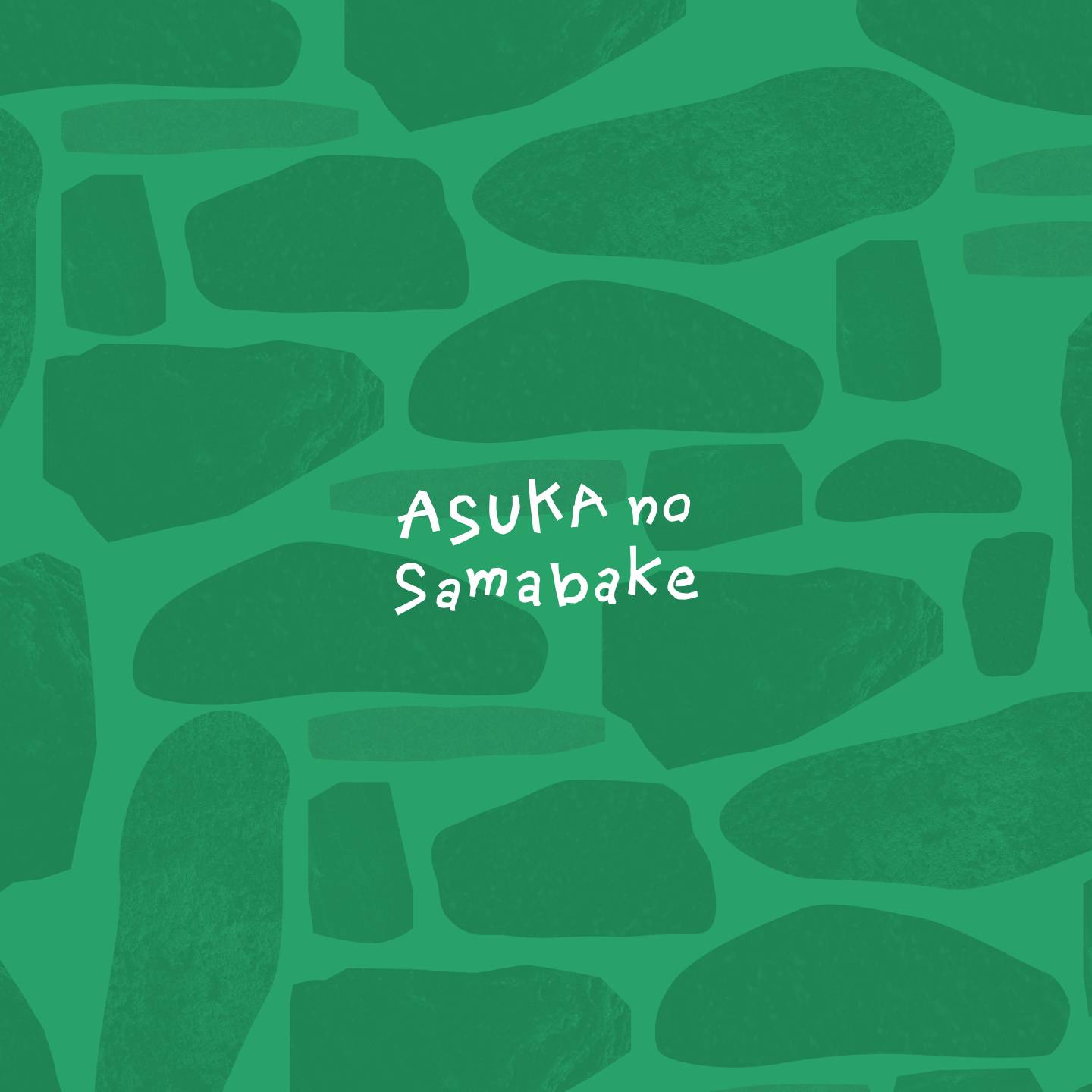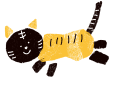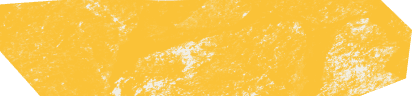サマバケ通信
samabake journal
文化も自然も満喫! 海獣葡萄鏡づくり&木の収穫体験!【体験レポート Vol.2】
- 文
- 坂東愛(飛鳥観光協会)
- 写真
- 都甲ユウタ

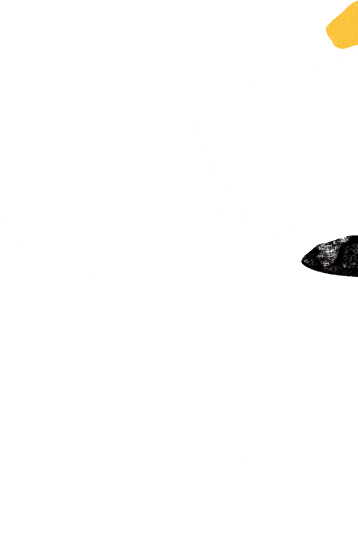




海獣葡萄鏡づくり体験
まだまだ夏真っ盛りの8月下旬。今回の主役は藤井あすみちゃん・まなみちゃん・航(わたる)くんの3人です。

藤井ママとお姉さんは母方のご実家が明日香ということもあり、昔からよく遊びにきていたそうですが、体験プログラムなどでの訪問は今回が初めてのこと。まだ行ったことのないエリアもあるそうなので、お二人にも新しい発見をしてもらうべく、出発です。
最初に向かったのは、キトラ古墳壁画体験館「四神の館」。明日香に数多く残る古墳のなかでも、キトラ古墳は石室内に極彩色の壁画が描かれていたことで知られています。隣接する「四神の館」ではさまざまなワークショップを行っていますが、今回は古墳とも関わりのある“鏡“づくりにチャレンジします。
ところで、キトラ古墳と同じく壁画で有名なのが高松塚古墳です。
約50年前の壁画発見は、当時押し寄せつつあった土地開発の波から明日香の風景を守る法整備(通称、明日香法)の後押しにもなりました。
今、明日香に多くの史跡や景観が残っているのは、この壁画のおかげ……といえるかもしれません。今回ワークショップで作る鏡は、その高松塚古墳から発見されたもののレプリカです。その名も「海獣葡萄鏡(かいじゅうぶどうきょう)」。なんだか強そうな響きですが、どんな仕上がりになるのでしょうか。
さて、四神の館のスタッフさんにやり方を教えてもらいながら、まずは素材になる金属を溶かしていきます。

小鍋に金属を入れて火にかけると、チョコレートのようにドロっと溶け始めます。


「溶けた、溶けた!」「すごい!」



この溶けた金属を型に流し入れ、熱が冷めたら型を外します。




「細かい模様がついてる!」「きれい!」



きちんと形になっていました。型に金属を流し入れる時に少しこぼしてしまい、失敗したかもと心配していた航くんも安堵の表情。ここからは、いろんなヤスリで磨いていきます。


ひたすら磨くこと約15分、徐々にツヤが出てきました。最初はぎこちなかった3人も、だんだんとこなれた手つきに。姿勢よくシュッシュと磨くあすみちゃん、まなみちゃんは手のひらの上で、航くんは細かく早く、磨き方にも個性が表れています。



時折、粉だらけになった手を見せ合いながらも、黙々と作業をする3人。

仕上げに研磨液で磨くと、一気に鏡のようにピカピカに。一番に完成したのは航くんでした。スタッフさんもベタ褒めだったその磨きぶりは、もはや職人! 鏡に映る嬉しそうな笑顔を見るに、時間をかけて磨いた甲斐があったようです。

できあがった鏡は想像以上に精巧な仕上がりで、よく見ると細かい文様が施されています。これらは名前の由来でもある「海獣」と「葡萄」のつる草で、「海獣」とは想像上の神聖な生きものを指すのだそうです。レプリカとはいえ、1000年以上の時を経て、当時と同じ鏡をつくっているのはなんだか不思議な感じです。
「まさか体験がこんなに楽しいとは思わなかった」と話す大人組も、無心で磨き、完成度の高い鏡に仕上げていました。日常で大人も子どもも同じように打ち込める機会というのは、案外そう多くないかもしれません。体験の様子を見ていると、ものづくりに年齢は関係ないのだなと感じます。

ちなみに、3人は完成品を夏休みの宿題として提出するのだと教えてくれました。夏休み明けといえば、教室の後ろに宿題の作品が展示されていた光景が思い出されますが、そこに海獣葡萄鏡が並んでいる様子を想像して、なんだかうれしくなりました。
体験が終わるやいなや、3人は「外で遊びたい!」と、駆け出しました。

走り回ったり、虫を捕まえたり、元気いっぱいの3人。並びは真ん中に航くんというのが定位置だそう。仲の良さが伝わってきます。


最初よりだいぶ打ち解けてきた3人と一緒に遊ぶ傍ら、明日香が昔より随分きれいに整備されたことや、のんびりした雰囲気や自然が好きなことを藤井ママが教えてくれました。ちなみにお姉さんは、古墳が大好きなのだとか。
今は法によって保護されている史跡のおかげで、こうした明日香の自然や佇まいも結果的に守られてきたのかもしれません。はるか昔の足跡による恩恵を今の私たちが受けていると思うと、なんだか感慨深いものがあります。
翌日の木の収穫体験に期待を膨らませながら、この日はここでお別れです。
木の収穫体験

二日目。お天気に恵まれ、朝8時でもすでに日射しが痛いくらいです。集合場所から案内されて最初に向かうのは、飛鳥駅からほど近いところにある小さな林。
足を踏み入れると、高い木々が密集して空を覆っています。このままにしておくと木が育って、日の光がどんどん入りづらくなるため、適度に間引き人の手を加えることで、残された草木が育ちやすい環境になるんだそうです

ということで、この日チャレンジするのは、この高くそびえ立つ木の伐採です。インストラクターは森や木の仕事に携わる久住一友(くすみかずとも)さんと渡邊祐示(わたなべゆうじ)さん。

久住さんは12年ほど前に明日香村へ移住し、林業を営みながら、森のある暮らしを日常にする実験室「森ある暮らしラボ」を開設するなど、さまざまな形で森に関わっています。

参加者は大人も合わせて20名ほど。2班に分かれ、それぞれ1本ずつ、のこぎりで幹に切り込みを入れたのち、ロープで引っ張って倒していきます。
いきなり一人でのこぎりを扱うのは難しいので、大人と一緒に作業する子どもたち。せっせとのこぎりを動かして、順番に切り込みを深くしていきます。藤井ファミリーの番がきました。航くんが藤井ママと挑戦です。

慣れない手つきで一生懸命のこぎりを動かしますが、刃が木に引っかかり、なかなかうまく切れません。日陰ではあるものの、ムシムシする林の中。暑さに加えて、蚊による虫さされもあってか、段々とやる気を削がれ、少しして他の子にバトンタッチしてしまいました。ちょっとだけ険悪ムードの3人……仲が良い分、よくケンカもするんだそうです。
ここで、久住さんがすかさず提案をしてくれました。


じゃあ3人でロープを引っ張ってくれる?


この言葉に俄然張り切りだす航くん、目に輝きが戻ってきました。

切り込み入りの木に括られたロープの先にはウィンチが取り付けられており、レバーを繰り返し動かすことで木を引っ張る仕組みになっています。引っ張れば引っ張るほど力がいる作業で、航くんが一人で挑戦するもなかなか難しそう。力を入れすぎて滑ってよろける場面もありましたが、それでも楽しそうです。

ここで、見かねたあすみちゃんが助太刀に。「せーの!」でタイミングを合わせながらレバーを動かすと、さすが2人力。ウィンチが「カチカチカチ」という音を立てて、ロープを巻き取っていきます。
3人で交代しながらこの作業を続けるうちに、「ミシミシ」という音と共に徐々に木が傾いていくも、周りの木の枝に引っかかったりして、なかなか倒れません。ここでまなみちゃんが「3人でやろ」と声をかけ、3人一緒にレバーを動かし始めました。

軋む音を大きくしながら傾いていく木を見て、自然と「ガンバレ!ガンバレ!」と周りから声援が聞こえてきます。そして、ついにドーンと勢いよく木が倒れた瞬間、わーっと歓声と拍手が起こりました。息が絶え絶えになりながらもやり切った3人、お見事! それぞれの額には大粒の汗が光っていました。

さて、ここからは工作タイムです。切り倒した木を丸太サイズにカットしてもらった子どもたちは、川に浮かべる小さな木船をつくります。

未就学や低学年の子たちが多いにもかかわらず、久住さんに工具の使い方をレクチャーしてもらう間、子どもたちからは次々と質問が飛び出し、久住さんも驚くほど。ひとたび興味をもてば、子どもたちはすごい集中力を発揮するようです。

まずは加工しやすくするために、丸太を鉈(なた)と棒で叩き割りながら小さくしていきます。

最初にまなみちゃんが挑戦するも、鉈がうまく丸太に入っていきません。刃を当てる位置によっては木が堅く、鉈が入りにくいのです。

久住さんいわく、こういう時は「気合で!」。まなみちゃん、「お母さんがやったらあかん!」とママの手助けを退けます。鉈の向きを調整したり、棒で叩く場所を変えたり、自分で考えながら何度も試し、ついにパカンと割れました。ブラボー!
続く航くんは、「君、木こりになれるよ!」とママが声をかけるほど、スパーンと気持ちよく割れました。鉈を叩く際は振動で手が痛くなるようで、あすみちゃんも時折痛がりながら頑張ります。

ああしたら、こうしたら、と意見を交わしながら家族で作業する様子は一体感があり、なにより、とても楽しそう。他の参加者の皆さんも次第に慣れてきたのか、木魚のようにポン・ポン・ポンと木が割れる音が心地よく林の中に響きます。

切りたての檜は香りがとても強く、“新鮮”という言葉がしっくりきます。普段よりも五感が研ぎ澄まされている気すらしてくるから不思議です。
作業は途中ですが予定時刻も迫ってきたので、川のある自然豊かな「奥明日香」エリアに移動します。藤井ママも初めてという奥明日香は、空気も澄んでいて心なしか涼しく、夏には特にうれしい場所です。

さあ、到着したら船作りの続き……のはずでしたが、子どもたち、一目散に川に向かって走り出しました。しっかり水着に着替えています。

「見て!」と言って見せてくれたのは、両手いっぱいの貝。飛鳥川の上流に位置するこの辺りは、水もきれいで魚や貝、カエルなどいろんな生きものがいるようです。船作りは一時中断になりましたが、それだけ子どもたちにとって川は魅力的な場所なのかもしれません。
足を入れると、流れは思ったより早く、水もひんやり冷たいことに驚きます。場所によっては意外と深さがあり、大人でも少しなら泳げそうです。実際に体験してみないと気づかないことが多くあると、改めて気づかされたような気がしました。

しばらくしてから、まなみちゃんが船を作りに戻ってきてくれました。小さく切った2枚の板にドリルで小さな穴を開けたら、そこに木の枝を差し込み最後に葉っぱで飾りつけて完成です。


早速、船を流すまなみちゃん。みんなが見守る中、スイスイと進む船、まなみちゃんも嬉しそうです。

「こうして川が流れているのは森のおかげなんです」と、最後に子どもたちに伝える久住さん。
森は雨水を蓄え、地中で浄化された水はやがて川へと流れていきます。「山」が十分な保水力をもつためには様々な樹木や草花で構成された「林」や「森」である必要があります。こうして自然の中に身を置いていると、古来より、人と自然は関わり合いながら生きてきたのだということを実感できるような気がします。

思い思いに川を満喫したのちお別れとなりましたが、明日香を発つ前に、事務所のある「飛鳥びとの館」にもう一度会いにきてくれました。また来てねとハイタッチして今度こそお別れ。2日間と短い時間でしたが、それでも最後は名残惜しい気持ちになります。明日香での滞在が、時折ふっと思い出すような、そんな体験になってくれていたら嬉しいなと思います。

守り守られ、自然や史跡、人々が共存してきた明日香。そこにさまざまなバックグラウンドをもつ人々が新たに集い、より多様な魅力が生まれていることを、今回改めて感じました。そして、そこには大人たちが気づかない、たくさんのワクワクが眠っている……それを気づかせてくれたのは、子どもたちでした。自ら楽しみを見つけていくその姿に、まだまだ明日香に秘めた可能性があることを教わったような気がします。