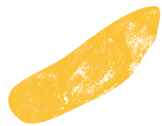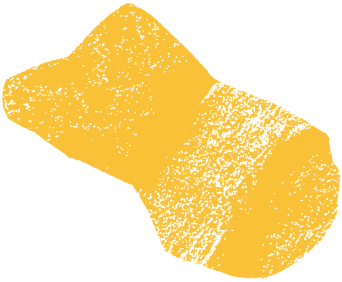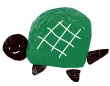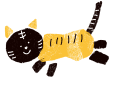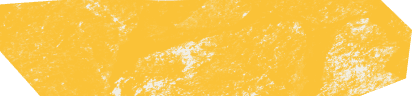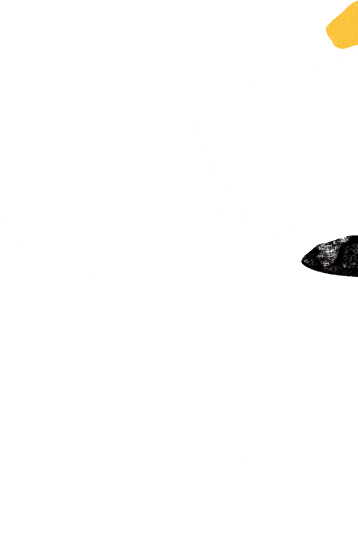




私は森林インストラクターとして、長年明日香村で自然と係わってきました。1995年、「飛鳥里山クラブ」一期生、「棚田オーナー」一期生、同時に稲渕で国蝶オオムラサキの飼育、当時の栢森総代と「森の手作り塾」をスタートし、また県農林職の方と「山守の会」を結成しました。


1999年には「サンワみどり基金(現三菱UFJ環境財団)」の支援で、女淵の滝を基点に、畑谷川両岸地域を昭和初期の景観に戻すことを目指す「飛鳥川の原風景を取り戻す仲間の会」を発足し、以来活動回数は126回を数えます。


これらのボランティア活動を通して、森林の荒廃や自然の変容に直面し、2つの深刻な状況を目の当たりにすることになりました。1つ目は、森林・中山間地域の人手不足です。担い手世代の高齢化と次世代の兼業化で手入れが行き届かなくなっているのは、長年ずっと語られてきました。そして2つ目は、森や自然と人間の係りが途切れつつあることです。

私は、森や自然が人間の身近な生活にどのように活用されてきたのかをみんなで体感してみたいと思い、「森の手作り塾」を始めました。明日香村地域振興公社が「オーナー制度」に組み入れてくれて、都市部の人々も順調に集まりました。
野草教室、藍染、芋峠への古道復活整備、栢森集落の「八朔」行事参加、つる細工、ワラジ作り、こんにゃく作り、しめ縄・赤米餅つき、シュロの箒作り、阪田での炭焼き、椎茸の植菌。やり方を教える地元側は、教える時間を通じて自信を取り戻し、教わる人々は「自然は工夫次第で身近に使えること」を楽しみながら学びました。







草木染は栢森や入谷で行っていましたが、2015年、縁あって立部で工房「水谷草木染」を開きました。築91年の古民家で、改修に7年かかりました。明日香の土の上にしっかりと根を張り、伝統の模様と植物の色に特化した体験教室にしようと思いました。大好きな植物で昔と今をもう一度結ぶ仕事に、今後の人生の時間を費やそうと決心しました。

植物の色との出逢いは「山守の会」の間伐作業時に遡ります。杉檜の間伐は皮剥ぎまでするのですが、その際滲み出てくる樹液がそれは美しく、心癒される桜色だったのです。樹木がこんなにも美しい色を持っていることに大変感動しました。

草木染は生きた植物の実、葉茎、皮、根を使います。澄明な美しさの決め手は鮮度です。しかし時間の経過と共に湿度や空気との摩擦でさえ色が薄くなり、茶色に帰結します。その移ろいは現代人にとってはマイナス要因ですが、昔の人々は色落ちの度に何度も重染めをして、克服していきました。私は体験の最初に、この草木染の生きた色である故のいわば宿命について丁寧に説明して理解をお願いしています。

古代には絞り染めの纐纈(こうけち)、板締めの夾纈(きょうけち)、ろうけつ染の﨟纈(ろうけち)の3つの染色方法があります。工房での模様は後世に沢山見本が伝えられている「板締め」の技法を主力にしました。


使う道具は手、棒切れ、板切れの3つです。固定は輪ゴムを使いますが、古代の紐「カラムシ」の皮を用意し、実際に引っ張ってもらい、紐としての強度を納得してもらっています。


明日香の地での草木染なので、判明している古代の模様にこだわりました。雲、波、虹の模倣、円、星、ミツウロコ、花、亀甲、竹、市松などの板締め、幾何学模様、てるてる坊主、線対称など、展示しているすべての模様の意味や技法を説明しています。

「昔の人ってすごいな〜」との賞賛の言葉が聞こえるようになります。素朴な3つの道具で作り出される多様な模様が、古くさくなく、斬新で、取り入れようとしてくれている気持ちがビンビンと伝わってきます。

染色に使う植物は、なじみがあり、かつ有用活用されていない8種類を用意しています。ビワは樹皮で冷染し明るいピンク色。タマネギは大量の皮で金色の輝き。

赤米は万葉植物であづき色。セイタカアワダチソウは葉茎で爽やかレモンイエロー。タンニンはクリイガで茶色。スモモは樹皮で紫。クチナシは実で山吹色。アカネは根で深紅色。

今でも毎回染める瞬間美しい本来の色が出ているかドキドキします。植物の発色は極めて繊細で、季節毎の生育状況、気温、天候、鍋の沸騰の有無などに影響を受けます。

昔さながらの染め方で、効率を考えない単調な動作を繰り返す染め場ですが、苦情が出たことはありません。それどころか、みなさん喜々として集中されます。

植物がどっさり入った鍋の羅列に「うわ!すごい!」の感想。「タマネギの皮放ったらアカンわ」「クリのイガ拾とこ」「セイタカアワダチソウっていいとこあるやん」など、今までとは違った視点の言葉が飛び交います。圧巻の模様開きは鮮烈な模様と目を見張る鮮やかな美しい色に感動の歓声が上がります。

昨年1回目のサマバケに参加し、ご家族全員が活き活きと集中して楽しまれる様子を拝見しました。人と自然との距離感を少しでも縮めていると実感する、嬉しい希望を持てる時間です。
体験される方々が「素敵な模様!」「きれいな色!」と喜ばれるのは、私にとって何にもかえ難い大きな喜びです。体験者さんとの共有の時間を持てる今、「工房をやっていて良かった」と満たされています。
▼この寄稿者が開催している体験プログラムはこちら
明日香の自然の恵みで「草木染体験」
http://samabake-asuka.com/program/902/